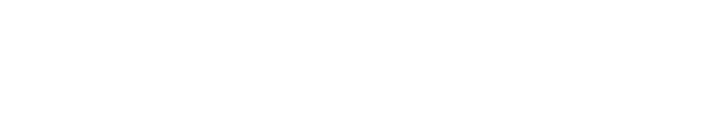最近は「インプロのファシリテーターになるにはどうしたらいいですか?」と聞かれることが増えてきました。また、去年からはインプロのファシリテーションの講座やワークショップを開いてきました。その結果、インプロのファシリテーターになるためには大きく3つのステップがあると思うようになりました。(自分自身がある程度インプロを学んでいることは前提です。)
そこでこの記事では、インプロのファシリテーターになるための3ステップを紹介します。また、それぞれに対応するインプロアカデミーのクラスもありますので、そちらも紹介します。
- 自分の現場にインプロを取り入れてみたい方
- インプロワークショップをやってみたい方
- インプロに限らず、ファシリテーションの学びについて知りたい方
にとって参考になると思います。ご興味ある方はぜひお読みください。
1. インプロゲームを知る
インプロのファシリテーターになるためには、まずはインプロゲームをたくさん知るところから始まります。具体的には、基本的なゲームを20個ほど知っておくといいでしょう。
また、この時にはただゲームのルールを知るだけではなく、ゲームの目的を知っておくことも大事です。それを知らないとインプロゲームが「学びにつながるゲーム」ではなく「楽しいだけのゲーム」になってしまいがちです。(僕はこれを「インプロゲームのパーティーゲーム化」と呼んでいます。)
このステップを学びたい方はインプロファシリテーター講座のインプロゲーム編がおすすめです。ファシリテーションしやすいインプロゲームを、ゲームの目的付きでシェアしています。
2. ワークショップを学ぶ
インプロゲームをたくさん知ったからといって、インプロワークショップができるようになるかというと、そうではありません。インプロを通して参加者を導いていくためには、ワークショップデザインやファシリテーションを学ぶ必要があります。
ワークショップデザインとは、ワークショップを事前にプログラムすることです。こちらはだいぶ知的な作業です。それに対して、ファシリテーションは当日の様子を見て即興的に対応していくことです。こちらは身体性や在り方が問われます。
このステップを学びたい人にはインプロファシリテーター講座のワークショップ編がおすすめです。内海がワークショップをどのようにデザインしているか、ファシリテーションしているかを実践的にシェアしていきます。なお、この講座はインプロに限らないワークショップ力向上にもつながります。
3. 自分自身の器を広げる
インプロのファシリテーターになるための3ステップ、最後の段階(と同時に最も基礎となる段階)は自分自身の器を広げることです。
自分自身が実現できないことはファシリテーションするのが難しいです。たとえば、失敗を恐れているファシリテーターが「失敗してもいいんですよ」と言っても、参加者にはあまり響きません。反対に、失敗を恐れていないファシリテーターであれば言葉で言わなくても失敗できる場になったりするのがファシリテーションの難しく面白いところです。
自分の器を広げるためには、ファシリテーションとふりかえりの数をこなしていくことが大事ですが、同時にインプロの舞台に立つことをおすすめしています。なぜなら、舞台に立つと自分がどれくらいインプロのマインドを実現できているか、お客さんの反応によって知ることができるからです。言いかえるならば、本当の意味で「自分を知る」機会となります。
インプロアカデミーには発表会付きの3日間集中ワークショップがありますので、舞台に立ちたい人はこちらがおすすめです。仲間とともにインプロを深く学び、舞台に立つことで、自分の殻を破ることを目指します。
まとめ
この3つのステップは、ピラミッド構造的には「3. 自分自身の器を広げる」が一番土台となり、その上に「2. ワークショップを学ぶ」、さらにその上に「1. インプロゲームを知る」となっています。
ただし、インプロゲームを知らないことにはワークショップを学ぶのも難しいので、実際の学びのステップとしては1→2→3、もしくは1→3→2のようになります。
同時に、それぞれのステップはゴールがあるものではありません。僕もいまだに新しいインプロゲームに出会ったり作ったりすることがありますし、ファシリテーションについては毎回ワークショップ後にふりかえりをしています。また、自分自身を器を広げることはそれこそ人生を通しての探究だと思っています。
しかし、ゴールが無いことは辛いことではありません。むしろ、ゴールがあったらそこで終わってしまいます。旅と同じように、どこかに行き着くことが大事なのではなく、そのプロセスを楽しむことが大事なのだと思います。そんな旅に興味がある方はぜひクラスへお越しください。ともに旅に出ましょう。